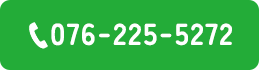日本肝臓学会
専門医・指導医による診察
 肝臓内科は、肝臓、胆嚢、膵臓の専門医療を行う診療科です。肝臓には感覚神経がないため痛みを感じない「沈黙の臓器」と呼ばれ、症状が現れるまで病気が発見されにくい臓器です。そのため、健康診断で肝機能検査をおすすめされた方や、慢性的な疲労感、倦怠感などの症状がある方は、できるだけ早い受診が推奨されます。問診では、現在の病気の状態、症状、既往歴、使用中の薬、手術歴、輸血歴、ご家族の既往歴などを詳しく伺います。その情報をもとに、当院で必要な検査を実施します。当院では、日本肝臓学会専門医・指導医、日本胆道学会指導医、日本膵臓学会指導医の資格を有し、大学病院での豊富な経験を持つ院長が診療や検査を担当します。
肝臓内科は、肝臓、胆嚢、膵臓の専門医療を行う診療科です。肝臓には感覚神経がないため痛みを感じない「沈黙の臓器」と呼ばれ、症状が現れるまで病気が発見されにくい臓器です。そのため、健康診断で肝機能検査をおすすめされた方や、慢性的な疲労感、倦怠感などの症状がある方は、できるだけ早い受診が推奨されます。問診では、現在の病気の状態、症状、既往歴、使用中の薬、手術歴、輸血歴、ご家族の既往歴などを詳しく伺います。その情報をもとに、当院で必要な検査を実施します。当院では、日本肝臓学会専門医・指導医、日本胆道学会指導医、日本膵臓学会指導医の資格を有し、大学病院での豊富な経験を持つ院長が診療や検査を担当します。
さらに、専門的な検査や治療が必要と判断された場合は、当院が連携している高次医療機関をご紹介し、患者さまに必要な精密検査や治療へとスムーズにお繋ぎします。
こんな症状や
お悩みはありませんか?
肝臓は悪くなっても症状が出ないことがほとんどですが、進行すると様々な症状が現れてきます。
肝機能障害が
進行してから現れる症状
- 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)
- 尿の色が濃くなる(茶色っぽくなる)
- 便が白っぽくなる
- かゆみ(特に全身の皮膚)
- むくみ(特に足や顔)
- 腹水(お腹に水がたまって膨れる)
- 鼻血や歯茎からの出血が増える(血が止まりにくい)
- 皮膚に細かい血管が浮き出る(クモ状血管腫)
- 手のひらが赤くなる(手掌紅斑)
など
肝機能の異常を指摘された場合
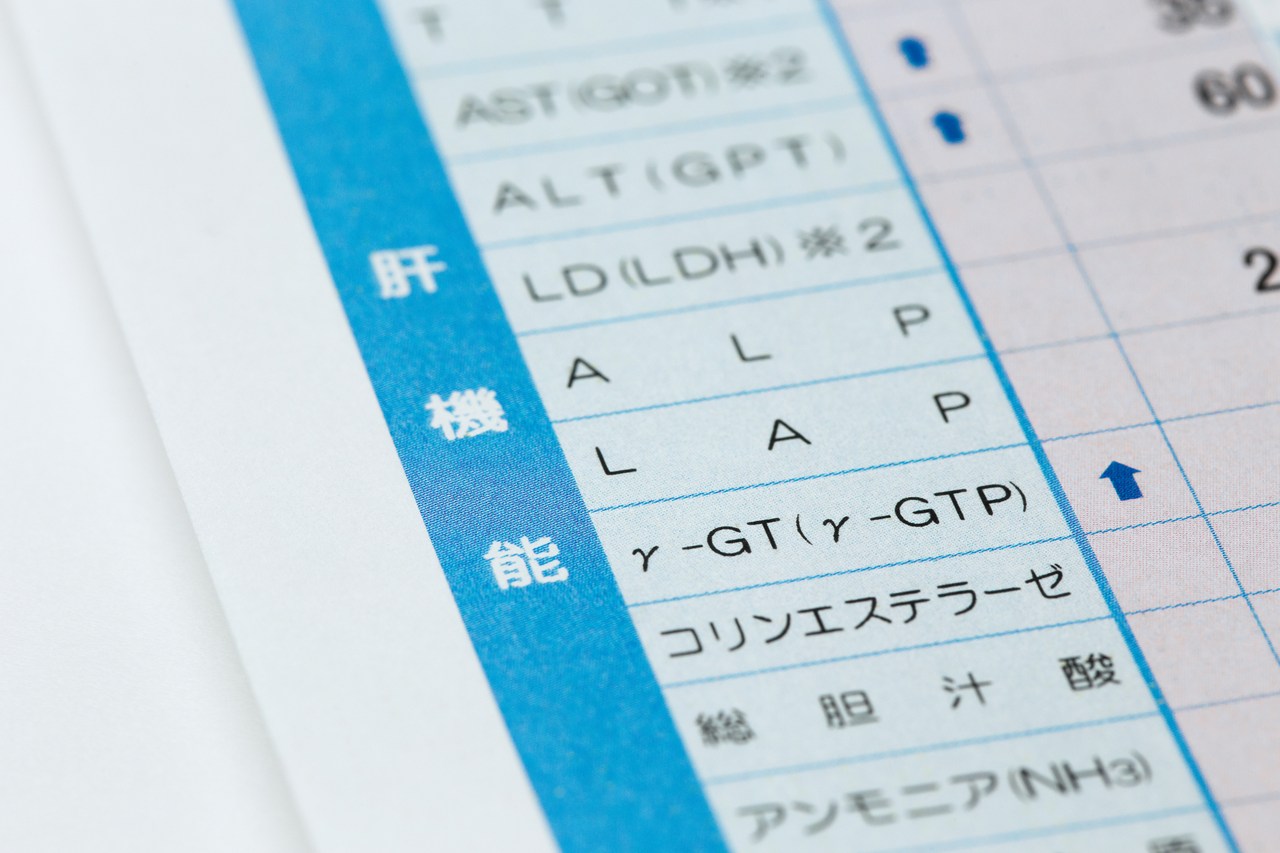
血液検査でAST、ALT、ALP、γGTPの値が異常である状態を「肝機能異常」と言います。これらの数値は、他の臓器の病気でも異常となる場合がありますが、肝臓の病気と関連することが多いため、「肝機能異常」と呼ばれています。
風邪や激しい運動など一過性の原因で数値が一時的に上昇することもあり、その場合は、再検査(精密検査)で正常になることもあります。また、お酒を全く飲まない方でも発症する「非アルコール性脂肪肝」や、B型肝炎、C型肝炎などの「ウイルス性肝炎」、自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎などの「自己免疫性肝疾患」も肝機能異常の原因となる場合があります。そのため、肝機能の異常を指摘された場合には放置せず、早めの精密検査をおすすめします。お気軽に当院までご相談ください。
肝機能の数値について
AST(GOT)
ASTは肝臓に高濃度で存在する酵素です。肝細胞が損傷を受けると、大量に血液中に放出され、数値が上昇します。ASTはアミノ酸を作る機能がある一方で、心筋や骨格筋など、肝細胞以外にも含まれているため、異常の原因を特定するためには後述のALT(GPT)値も確認する必要があります。ASTの基準値は30U/L以下ですが、この値以下であっても、通常は心配する必要はありません。
ALT(GPT)
ALTは、肝臓細胞に最も多く含まれる酵素です。ALT値が上昇すると、肝臓に何らかの異常が疑われます。ASTと同様に、アミノ酸の合成に関与する酵素であり、基準値は30U/L以下です。ASTと同様に、この値以下であれば、一般的に心配する必要はありません。
ALP
ALPとは、肝臓(胆管)、骨、腸、腎臓など、多くの臓器に含まれる酵素です。これらの臓器が損傷すると、ALPが血流に漏れ出し、ALP値が上昇します。しかし、ALPは胆汁にも排泄されます。そのため検査の数時間前に脂肪分の多い食事をとった場合も、ALPの値が上昇することがあります。なお、基準値は、検査を行う医療機関によって異なる場合があります。日本人間ドック学会は80~260U/L、国際臨床化学連合(IFCC法)は 38~113U/L、日本臨床化学会(JSCC 法)は 106~322 U/Lを推奨しています。なお、ALP の値が低すぎる場合にも、何らかの病気が疑われます。
γ-GTP
γ-GTPは、主に肝臓で働く酵素であり、体内の「解毒」に関わる重要な役割を担っています。この酵素は、肝臓や胆道系に異常がある時に数値が上昇するため、肝機能の指標としてよく用いられています。ただし、他の逸脱酵素と異なり、体内で解毒を必要とする状態、たとえば薬剤や飲酒などの影響で、明らかな病気がなくてもγ-GTPの値が高くなることがあります。
基準値は、男性で79U/L以下、女性では48U/L以下とされており、特に過度の飲酒習慣がある方では、このγ-GTPだけが異常値を示すケースも見られます。また、γ-GTPの値が極端に低い場合にも、健康上の問題を引き起こす可能性があります。
総ビリルビン
総ビリルビンとは、血液中に含まれる黄色い色素の値で、血液検査によって測定されます。この値が高くなるのは、肝臓や胆嚢、胆道に何らかの障害が生じている可能性がある場合で、結果として黄疸の症状が現れることがあります。ビリルビンは、寿命を終えた赤血球が分解される過程で生まれる色素で、本来は肝臓で処理された後、胆汁として体外へ排出されます。しかし、肝機能が低下すると、この処理や排出の流れが滞り、血液中にビリルビンが漏れ出して数値が上昇します。
ビリルビンには「直接ビリルビン」と「間接ビリルビン」の2種類があり、この両方の合計が「総ビリルビン」として表されます。いずれか一方、あるいは総ビリルビン全体の数値が正常値(0.2~1.2mg/dL)を超えている場合、何らかの病気が疑われます。ただし、中には体質的にビリルビン値が高めの方もおり、そのような場合は「体質性黄疸」と呼ばれ、必ずしも病的な異常を示すものではありません。
肝臓内科でよくある疾患
- 脂肪肝
- アルコール性肝炎
- 非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)
- 非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)
- 急性肝炎
- 慢性肝炎(B型肝炎・C型肝炎など)
- 胆嚢ポリープ
- 胆石
- 胆嚢炎
- 急性膵炎
- 慢性膵炎
など
肝臓内科での検査について
 肝機能に異常がある、またはその疑いがある患者さまには、さらに詳しい血液検査や腹部超音波検査を行います。血液検査では異常が見られない場合でも、再検査(精密検査)を行うと異常が見つかる場合があります。腹部超音波検査は、日本肝臓学会専門医・指導医、日本胆道学会指導医、日本膵臓学会指導医の資格を持つ院長が担当しており、肝臓だけでなく、胆道や膵臓も詳しく調べます。
肝機能に異常がある、またはその疑いがある患者さまには、さらに詳しい血液検査や腹部超音波検査を行います。血液検査では異常が見られない場合でも、再検査(精密検査)を行うと異常が見つかる場合があります。腹部超音波検査は、日本肝臓学会専門医・指導医、日本胆道学会指導医、日本膵臓学会指導医の資格を持つ院長が担当しており、肝臓だけでなく、胆道や膵臓も詳しく調べます。